レポート36 / 2017.08.23
本のグルメ「昔のレシピ」編
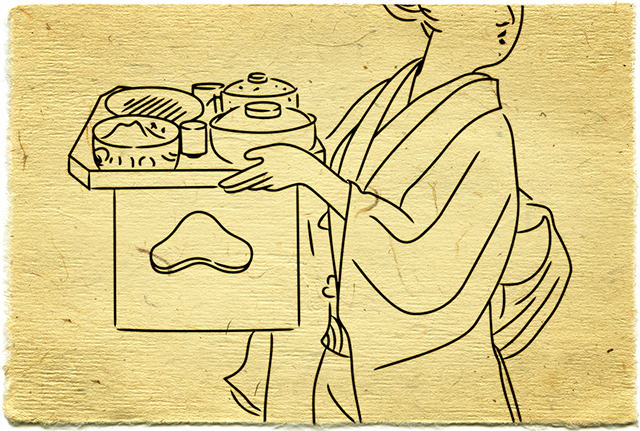
あの名企画、レシピ再現シリーズが帰ってきた。第2弾は「昔のレシピ」編。江戸~昭和初期までを5つの時期に分けて、実際に刊行された本や雑誌のレシピを再現してみようというもの。2013年に和食がユネスコ無形文化遺産に登録されて以来、自然の食材を使った昔の料理はますます注目を集めている。つまり、古いのに最先端、というわけだ。
滅多にお目にかかれない料理の数々。とくとご堪能あれ。
『江戸時代のレシピ』
参考資料を借りた「食の文化ライブラリー」でも、一番目立つ位置で特集していたのが江戸料理。食材は今や海外でもブームになっている豆腐、それも焼き豆腐を使う。江戸時代には通常の豆腐に比べ12分の1の価格だったという庶民的な食材だ。柔らかなボディを叩いてしまうのはかなり意外だが、そうすることで保存性が増し、冷めてもOKのアイデア料理に仕上がるという。
叩き豆腐

やき豆腐ふくさ味噌七分三分の分量にして菜刀にてひとつによくたゝき よきほどにとり油にてさつとあぐ(火偏に上が世、下が木)る也 調味好みに随ふ
(『豆腐百珍』醒狂道人何必醇 1782)
オープニングを飾るのにふさわしくシンプルな工程…のはずが、やっぱり問題発覚。単に焼き豆腐と味噌を固めるだけでは、油で揚げる時点でバラバラになってしまう。そこで、ためしに片栗粉を混ぜ込んで揚げたらうまくいった。レシピの完全再現といかないのは不本意だが、カタチにするためにはやむを得ない。外側に軽く小麦粉を塗ってみるのもよさそうだ。
叩き豆腐
【材料】
・焼き豆腐(1丁350g)
・味噌(150g)
・サラダ油(適量)
・片栗粉(少々)
【つくり方】
1.焼き豆腐と味噌をまな板の上に置き、包丁でたたきながら混ぜる。
2.1を丸く成形して、揚げる。
●実食
見た目はころころと可愛らしく、巨大な軟骨の唐揚げのよう。口に入れると、衣はサクッと軽く、中はふわっと柔らかく優しい食感。ただただウマイ。試食を手伝ってくれた子どもたち(1~2歳児)にも大人気だった。しいていえば、今回の割合(豆腐7:味噌3)だとちょっと味が濃いかもしれない。そこは分量を調節したり、つなぎを入れたりすればなんとでもアレンジ可能だろう。
まさか初っぱなからこんな当たりを引くなんて。江戸最高!
『明治時代のレシピ』
明治時代のレシピは、報知新聞に連載されて一大ブームを巻き起こした村井弦斎の『食道楽』(◯しょくどうらく × くいどうらく)から2品選んでみた。明治におけるこの本の影響力はすさまじく、ヒロイン「お登和」の名前がついた店ができたり、なんと舞台化までされたとか。著者・弦斎の手腕もスゴイ。自分の作品を納得いくまで加筆修正するため、出版社の原稿買い切りを嫌って自費出版に踏み切り、その売上で広大な屋敷を建築。和洋の野菜畑、果樹園、鶏やヤギなどの廐舎まで揃えて自給した。なんというスケール…。
田毎豆腐

「先ず餡掛豆腐の変体さね。四角に切た豆腐の真中を匙の先でくり抜いてその中へ玉子の黄身のザット湯煮たのを落してそれをそうっと沸湯で湯煮て別に葛の餡を拵えて掛けるのだが今日のは豆腐も柔に煮えているし餡の味も佳い。お徳や、今日のは別製かえ」
(『食道楽』村井弦斎 1903)
またまた豆腐料理で恐縮だが、今度は叩くのではなく、くりぬくタイプ。名前は長野県更科の「田毎の月」に由来している。この料理、作中では「日本も芭蕉の句なんか記憶してる場合じゃない。もっと役に立つ科学知識、たとえば卵の雄雌判別法なんかを身につけるべきだ――」とグダグダ小うるさい中川(お登和の兄)を黙らせるために出されている。
田毎豆腐
【材料】
・豆腐(1丁)
・卵(黄身のみ)(1個)
・葛粉(適量)
あんかけ
・だし汁(適量)
・しょうゆ(適量)
・みりん(適量)
・葛粉(適量)
【つくり方】
1.葛粉を入れたお湯で豆腐をゆで、温まったら豆腐だけ器にあげる。
2.豆腐の表面中央をスプーンでくり抜いて、そこへ卵の黄身をのせる。
3.だし汁、しょうゆ、みりん、葛粉を混ぜてあんかけをつくる。
4.2に3をかけて完成。
スムーズに完成。奮発して(小袋で600円超え!)吉野葛を使用したせいか、片栗粉よりも葛の透明感がそこはかとなく上品な気がした。豆腐に対して黄身が小さいような気がしたが、そこはまあ、名月でもたまたま小さい日はあるだろうということで…。
●実食
何ともかわいらしくて、食べるのがもったいない気持ちになる。滑らかな豆腐の食感と黄身のまろやかさ、出汁の風味が口の中で混ざり、卵豆腐のような味わいが広がった。葛あんは上品でやや苦みあり。のどごしが良いのであっという間になくなってしまう。
クセがない美味しさで嫌いな人は少ないだろうが…パンチはない。試食の途中で「揚げ出し豆腐のほうが好き」と言い出す不届き者がいた。
リンゴのフライ
「林檎のフライは林檎の皮を剥き心をとり薄く切り別に玉子と米利堅粉あるいはウドン粉へ塩と砂糖にて味附ける濃きころもを作り、それへくるみてフライ鍋にて揚げる。
上等製の林檎フライは前文の品をブランデーと砂糖に一時間漬けおき、玉子の黄身と米利堅粉とを牛乳にて溶きかつねりて固くし、白身を泡立たせてそれへ交ぜるなり。油にて揚げる時最初は火を弱くして緩々揚げ後ち火を強くして卸すべし。」
(『食道楽』村井弦斎 1903)
いったん気分を変えてスイーツへ。原作ではフライのほかに、裏濾しした林檎とゼラチンと混ぜ合わせる「泡雪」という料理も紹介されている。お登和さんがあまりにも熱弁するので興味深かったが、今回は他にゼラチン料理をつくる予定なのでスルー。
ちなみにリンゴのフライの章では、前述の中川が主人公の大原に向かって「君も早く嫁をもらえ」と言い、大原が「またそれを言う。泣きたくなるよ。今夜はお登和さんを夢に見よっと!」と居直る寂しいくだりがある。
リンゴのフライ
【材料】
リンゴベース
・リンゴ(1個)
・ブランデー(大さじ1)
・砂糖(大さじ1)
衣
・卵(1個)
・砂糖(大さじ1)
・小麦粉(大さじ2)
・牛乳(少々)
・サラダ油(適量)
【つくり方】
1.リンゴは皮をむいて芯をとり、5ミリくらいの厚さに切る。
2.ブランデーと砂糖を混ぜた中に1を漬け、1時間ほど置く。
3.ボールに卵の黄身と砂糖を入れてよく混ぜ、小麦粉を入れてざっと混ぜる。
4.別のボールに卵の白身を入れ、器を逆さにしても落ちないほどよく混ぜる。
5.3に牛乳を加え、4を入れて混ぜる。
6.2のリンゴに5の衣をよくつけて、フライ鍋の油の沸き立ったところへ入れる。最初は弱火で気長に揚げ、もうできたと思うときに、いったん火を強くしてからリンゴをキッチンペーパーに上げる。
もちろん豆腐も大好きだが、ブランデーの染みたリンゴはなにやらオシャレでテンションがあがる。このまま見目麗しい料理が完成…とはいかなかった。気長に揚げすぎたのか、リンゴが油をたっぷり吸いすぎてしまった!見るからに油ギッシュなフライドポテト、もといフライドアップルをいざ試食。
●実食
食べた瞬間、このシリーズにしては珍しく意見が分かれた。基準はズバリ年齢。20~30代の研究員は2つ3つと手が伸び、ついでに子どもたちの手も伸びる。が!40代から突然難色を示しはじめた。思い当たる読者の方は焼きリンゴにして置いた方が無難だろう。
衣を取った中身はとにかくおいしい。薄く切ったリンゴの微かなシャキッとした食感、ブランデーの酸味の組み合わせがかなりの高評価だった。ちなみに、そこら辺にあったバナナも適当に揚げてみたら青臭さがキツく大失敗。生ものにはちゃんと下味をつけよう。
『昭和初期のレシピ』
1917 年(大正6 年)に『主婦の友』が創刊。大衆層に向けた料理雑誌として人気を博した。この時代から料理の完成形が写真で確認できるようになり、つくり方も通常の文章ではなく、いわゆるレシピ形式に。現在の料理本の源流をつくった。
今回は2013 年に主婦の友社から発行された『温故知新で食べてみた』(山本直味・著)から、85年前の料理を2 品ピックアップ。レシピはまるまる引用すると長すぎるので、これ以降の時代については、冒頭の紹介文のみの引用に留めたい。
干魚のポテト詰め

暑さで、食慾のないとき、焼きたての香ばしさが、食慾をそヽります。干物は、魳が一番美味しいですが、鰺などでも結構です。
(『主婦の友』昭和7年7月号 1932)
『温故知新で食べてみた』に紹介されている料理はどれもなかなかのインパクトだ。焼きたての香ばしさが食欲をそヽります、といわれても...もっとすごいことが魳には巻き起こっているじゃないか。
干魚のポテト詰め
【材料】
・魳(カマス)の干物(1尾)
・じゃがいも(1個)
・バター(適量)
・トマト(輪切り2切れ)
・パセリ(少々)
【つくり方】
1.じゃがいもをゆでて皮をむき、フォークの背を使ってつぶす。
2.干魚(ひもの)の身にバターをぬり、半身に1を形よくのせて、両方の身をあわせる。
3.魚焼きグリルで香ばしく焼く。
4.3を皿にのせ、トマトとパセリをかざって完成。
単刀直入に腹を割って話すけれど、我々は凡ミスをした。本当は腹の中にポテトを入れる料理なのに、背中側が空いた魳を買ってきてしまった。申し訳ない。 この料理は基本的に、マッシュポテトをつくれば終わり。あとは買ってきた干物の風味にマッチしてくれるかどうかを祈るばかりだ。また、レシピには書かれていなかったが、今回は子どもが食べるので丁寧に骨を取った。そういう意味では鰺より魳のほうがオススメ。マッシュポテトを背中にたくさん詰め込んで、料理は完成。
●実食
インパクトは最大級。味のイメージとしては、わかりやすく言えば芋の山の中からにょきっと魳が顔出すような感じ。うまく相乗効果が起こらず、別々の方がうまいという声が大半だった。ただ、あまり魳を食べない研究員にはその上品な美味しさが評判に。カマス。良かったらこの機会に漢字を覚えてあげてほしい。
カステラのゼリー

ジャムはこの他、苺、葡萄、何でも結構。カステラは一本二十戦くらゐの安いもので、パンを代用しても無論よいのです。
~中略~
十分冷めてから召し上がってください。とても美味しいですから。
(『主婦の友』昭和7年7月号 1932)
カステラ、バナナ、ゼリーに加えて、桃のジャムを使用。子どもが泣いて喜びそうなオールスター料理だ。元のレシピには5人分をボウルでつくると書いてあったが、かなり甘そうなので2~3人分にアレンジさせてもらった。おそらく当時の平均的な家庭が5人だったものと思われ、こんなところでもしみじみと時代の違いを感じさせられた。
カステラのゼリー
【材料】
・カステラ(3切れ)
・バナナ(1本)
・桃ジャム(適量)
・寒天(4g)
・水(500ml)
【つくり方】
1.カステラ2切れをさらに縦半分に切り、器の底に敷いて、表面に桃ジャムをぬる。
2.1の上中央にカステラ1切れをのせる。
3.バナナを1センチ幅に輪切りにして、2のまわりと中央にならべる。
4.粉末寒天に熱湯(80°C以上)を入れ、溶かす。
5.3に4を流し入れ、冷蔵庫で固まるまで冷やす。十分冷めたら完成。
つくっている最中にさまざまな疑問がわいた。カステラに桃のジャムを塗ってさらに甘くする理由もわからないし、カステラとバナナの組み合わせもモヤモヤする。極めつけは寒天をしみ込ませて固めるという暴挙。スプーンで混ぜるとぐにゃっ、プルン、とろーんと色んな感触が伝わってきて、カステラにいたってはぶくぶく泡が出てきた。仕上がりはつやっとして涼しげ、時期的にはぴったりだが…。
●実食
シェフを呼んでこい、殴りたいから。という超問題作。だが残念ながらつくったのは我々だ。桃ジャム入り寒天は、なんとほとんど甘味を感じない。味の薄い寒天がやっとのことでどこかへ去ると、これまた味のないカステラがもっさりと口に居座り、そこにバナナが割り込んで主張を始める。それぞれの食材が足を引っ張うドタバタ劇。泣いて喜ぶどころか違う意味で泣きそうだと、あわてて子どもたちの口を隠した。
中でも一番に罪深いのは水分を含んだカステラ。噛むたびに堅い寒天が飛び出してくるのはまさにありがたくない新食感で、料理における食感の大事さをまざまざと思い知らされる結果に。食後、原本の紹介文「とても美味しいですから」がいつまでも脳裏にリフレインしていた。
『戦時中のレシピ』
続いては戦時中。婦人雑誌や、民間で伝わった料理をまとめた『戦下のレシピ――太平洋戦争下の食を知る』(斎藤美奈子・著)を参照した。他の時代とは目のつけどころがだいぶ違っていて、「節米」「蛋白質」といったキーワードが頻発する。序盤は気の利いた食材もちらほら登場するが、ページが後半に進むほど切実になり、「どんぐり」「道端の雑草」「濃厚塩水」といった崖っぷちの食材が登場する。
胡桃ビーフ
お肉を使わないのに肉の味がする面白いお料理です。胡桃は植物性の食品の中では脂肪も蛋白質も優れ、栄養価の高いものですから、日本でももっと増産して、一般の人が食べるようになるとよいと、婦人は熱心にすすめられました。
(『婦人の友』昭和15年10月号 1940)
胡桃ビーフ
【材料】
・胡桃(皮ごと)(180g)
・たまねぎ(1個)
・卵(2個)
・ご飯(カップ4)
・バター(適量)
・塩(小さじ3)
【つくり方】
1.胡桃をきざみ、すり鉢でする。
2.たまねぎの半分をみじん切りして炒める。
3.1の胡桃、2のたまねぎ、卵、塩をご飯によく混ぜ合わせる。
4.大き目のどら焼きくらいの形に成形して、両面をバター焼きにする。
5.残りのたまねぎを輪切りにして塩を振り、バターで炒めてお湯をさし、蓋をしてしばらく煮る。
6.4に5をのせて、お皿に盛る。
なんとか肉を食べよう、米をかさ増ししようという試みでつくられたこの料理。せっかくなので胡桃は食感を残すように粗くすってみた。生胡桃を使ったが、乾煎りしてから混ぜたほうが香ばしくてよかったかもしれない。 仕上がりは、焼きおにぎりそのもの。
●実食
輪切りのタマネギが乗っていてかわいい。戦時中の料理なのに、今回つくった料理のなかでトップクラスにオシャレだ。さっそく一口ガブリ。バターと塩の効いた味とくるみの食感はさすがに食べ応え満点だ。さすがに肉の味というには無理があるが、そぼろ入り焼おにぎりくらいには見栄を張ってもいい。玉ねぎも香ばしく、全体的に好評だった。
彩りにパセリがほしい...などと欲しがってはいけない。ぜいたくは敵だ。
『戦後のレシピ』
ずっと飛んで1960年代。カラーテレビの時代、ついにカラーレシピも手に入るようになった。この時代で参考にした本は、2016年のNHK連続テレビ小説「とと姉ちゃん」でも記憶に新しい『暮しの手帖』。第60号に登場する「スパゲチの冒険」から2品を選んだ。言うまでもないがスパゲチ=スパゲッティ。思わず口に出したくなる素敵な表記だ。
「たくさんの試作の中で、いくつか新しいおいしい料理法がみつかりました。この冒険は、どうやら成功したようにおもいます」と丁寧かつ強気な宣言ではじまる大冒険。結末やいかに。
うなすぱ

つけ汁にうなぎの蒲焼きを入れ、スパゲチを冷しそうめんふうにたべようというわけです
こってりしているようで、案外口あたりのさっぱりした、しゃれた味です
(『暮しの手帖』第60号 1961)
原本には「うなすぱ」という料理名がゆるめの手書き文字で書かれていて、東海林さだお先生を思い出した。創刊者・花森安治は「文章は話すように書け」の格言で知られる人物。気軽に読める文体には、どことなく共通点が見受けられる。
うなすぱ
【材料】
スパゲッティ
・スパゲッティ(450g)
・塩(小さじ1)
つけ汁
・うなぎの蒲焼き(1串)
・みりん(1/2カップ)
・しょうゆ(1/2カップ)
・だし汁(2.5カップ)
【つくり方】
1.塩を入れた多めのお湯で、スパゲッティをゆでる。
2.うなぎの蒲焼きはひと口大に切る。
3.みりんを煮切ってから、しょうゆを入れて煮立てる。それをだし汁でのばし、2のうなぎを入れて、中火で10 分ほど煮る。蒲焼きのタレがあれば一緒に入れる。
4.どんぶりに冷たい水をはってスパゲッティを入れ、氷を浮かせる。3のつけ汁は、器にそそぎ入れる。
つくる上での問題点は何もなし。久しぶりにめんつゆの素ではなく、ちゃんとつゆをつくった気がする。
●実食
意外さはないが、予想よりずっとハイクオリティな味わい。だし汁はコクがあって栄養満点だし、冷やしたスパゲッティもコシのある細麺うどんのようで合っている。麺がツルツルすぎてとてもつゆに絡まなそうに思えたが、蒲焼きという具があいだに入ってしっかりカバーしている。甘辛と香ばしさにどんどん箸が進んだ。
白ソースかけ

パセリは飾りみたいですが、じつはビタミンAとC、それにカルシウムが、たっぷり入っています。これを口のなかでガサガサしないように、できるだけこまかく刻んで、たっぷりかけてたべようというわけです。
(『暮しの手帖』第60号 1961)
「冒険」と言いながらスパゲッティに白ソース(ホワイトソース)という王道の組み合わせ。逆に面食らってしまった。当時はまだ「コンソメ」という概念を取りいれてなかったせいか、塩コショウとバターだけで味付ける点が現在と違う。
白ソースかけ
【材料】
スパゲッティ
・スパゲッティ(450グラム)
・塩(小さじ1)
白ソース
・豚肉(100グラム)
・たまねぎ(1個)
・セロリ(1本)
・牛乳(4カップ)
・にんにく(1片)
・パセリ(適量)
・塩(小さじ2)
・こしょう(適量)
・バター(大さじ3)
・小麦粉(大さじ2)
・サラダ油(適量)
【つくり方】
1.塩を入れた多めのお湯で、スパゲッティをかためにゆでる。
2.豚肉とたまねぎは1センチの角切り、セロリは小口から薄切り、にんにくはみじん切り、パセリはカップ1ほどの量を細かく刻みます。
3.サラダ油を熱したフライパンでにんにくを炒め、たまねぎを入れる。たまねぎに色がついてきたらセロリと豚肉も入れて、塩とこしょうで味をつける。
4.別のフライパンにバターを溶かして、小麦粉を入れ色がつくまで炒め、牛乳でのばして白ソースをつくる。
5.4の白ソースに3を入れて5分ほど煮る。
6.スパゲッティを皿に盛り、上から5をかけ、パセリをたっぷりふりかけて完成。
見た目は大成功。ソースにダマができることもなかった。本に書かれている通り、たっぷりとパセリを振って彩りも鮮やかだ。まるで普通に夕食をの仕度を終えたような気分だった。あとは味が薄くないかだけが懸念材料。
●実食
あ、ウマイ。炒めた肉や野菜で十分コクが出ていて、ねっちりした白ソースにスパゲティが良く絡む。文句をつけるとすれば、やっぱり冒険が足りないということになるだろう。味が薄くなる以外にまず失敗する要素がない。パセリはやや多すぎた気もするが、栄養があるものはとにかく食べろというのが昭和流。戦時中に我慢した分、しっかり食べよう。
以上8品。時代ごとに料理を食べ比べてみた。いくら古いレシピとはいえ、いまは使わないような無茶な食材は載っていなかったし、全体的に想像していたよりも食べやすい。ぜひみなさんにも試してほしいが、海外の食材や電化製品が入り始めた昭和初期は、変に凝っているので要注意だ。
2014年に創設された「レシピ本大賞 in Japan」の歴代受賞作は、タイトルやコピーに”ラクうま””つくおき(つくりおき)”といった忙しい人向けのワードが並ぶ。そういう意味でも、最初につくった江戸料理・叩き豆腐がもっとも現代の時流をとらえているのはおもしろい。味も良く使い回しも利く、今回イチオシのメニューとなった。たまに地雷は踏むものの...やっぱり本のグルメはやめられない。



